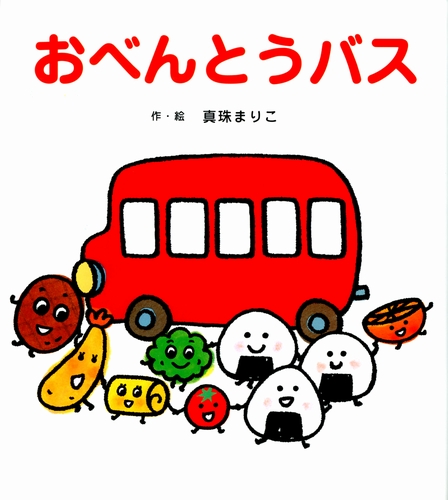「わすれられない おくりもの」
評論社の児童図書館・絵本の部屋
スーザン・バーレイ さく え
小川仁央 やく

前々回、死を題材にした絵本「いつでも あえる」という絵本について書きましたが、もう一冊 年をとり、死ぬのが そう遠くはないことを自身で悟っている アナグマと、その友達たちのお話「わすれられない おくりもの」という名作絵本について ブログを書こうと思います。
アナグマは賢くて、いつもみんなに頼りにされていました。困っている友達は誰でも助けてあげるし、また、知らないことはないというくらい、もの知りでした。
アナグマは自分の年だと、死ぬのが そう遠くはないことも知っていました。
アナグマ自身は、死ぬのを恐れてはいませんでした。からだはなくなっても、心は残ることを、知っていたからです。
だから、年を取り身体がいうことをきかなくなってきても くよくよしていませんでした。気がかりだったのは、自分のことではなく、後に残していく友だちのことを、あまり悲しまないでほしいと、心配していたのです。
でも、時の流れはとめられず、アナグマは本格的な冬の前に死んでしまいます。
「長いトンネルの むこうに行くよ さようなら アナグマより」
という手紙を残して…
悲しみに暮れる森の動物たち、長い冬の間、動物たちは泣き暮らします。失った喪失感は そう簡単に埋められるものではないでしょう。
寂しさや悲しい気持ち… でも 絵本「いつでも あえる」と同じく、残されたものの毎日は続いていくのです。
動物たちは 雪が消えはじめ、春の足音がきこえ始めたころ、外に出始め、互いにアナグマの思い出を語り合うようになると、気付き始めます。
アナグマが、たくさんの楽しい思い出とともに、ひとりひとりに
「別れたあとでも、たからものとなるような、ちえとくふうを 残していってくれたこと」に。そうして、少しずつ思い出を笑顔で語り合えるようになっていったのです。
物語の素晴らしさはもちろんですが、水彩とペンで描かれる優しい色彩の絵が素晴らしいです。
雪が解け始めたころに、雪の下から芽を出し可憐に咲くスノードロップの花が、みんなの悲しみにそっと寄り添い、溶かしていってくれていそうで、また、癒してくれているような感じで、印象に残ります。
また、アナグマが主人公だったり、スノードロップが描かれていたりと、イギリスの作者らしいところも感じます。
かけがえのない人を失って、悲しみの中にいる誰かの傍らに、何も言わず、そっと置いてあげたい絵本です。
※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。