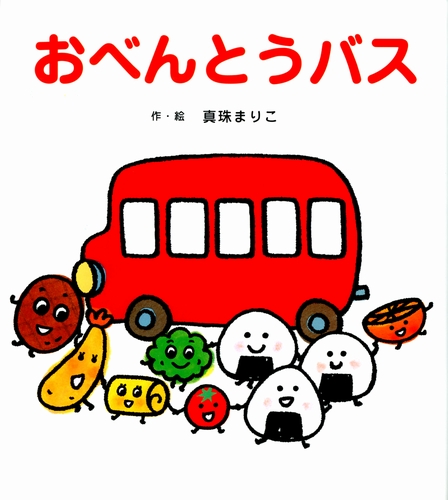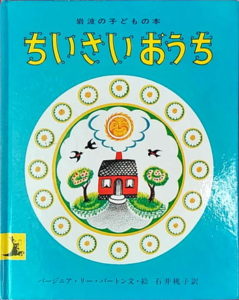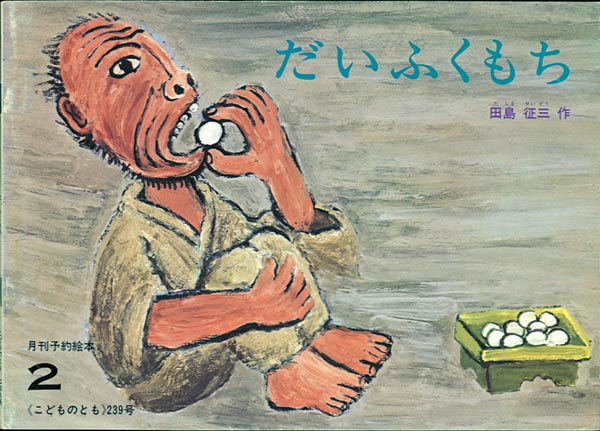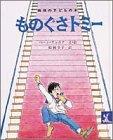「ぐりとぐら」
福音館書店
なかがわりえこ 文
おおむらゆりこ 絵

「ぼくらの なまえは ぐりとぐら
このよで いちばんすきなのは
おりょうりすること たべること
ぐり ぐら ぐり ぐら」
楽しい雰囲気で始まる、赤と青の帽子がトレードマークの、ふたごの野ねず「ぐり」と「ぐら」のお話。
いつも仲良しでお料理することと食べることが大好きな2ひきの野ねずみは、天気の良いある日、大きなかごを持って、もりのおくへ出かけます。
どんぐりや栗を拾いながら、歩いていくと、なんと、道の真ん中に、大きなたまごがおちているではありませんか。
2ひきの野ねずみより大きな大きな たまご、どうやって家まで持って帰ろうか…
どうやっても、もって帰れないと思ったぐりとぐらは、このまま、この森の中で
お菓子作りをしようということになります。
森じゅうに広がる美味しそうな、いいにおい…そしてそして、有名なエンディングへと、お話は進んでいくのです。
私が子どもの頃にも、よく母に読み聞かせをしてもらい、楽しませてもらいました。ふたりがつくった黄色い大きなカステラの場面は、憧れで、本当にいいにおいがしてくるような気がしたものです。
また、その場面には、以前にこのブログで紹介している「いやいやえん」に出てくるオオカミや赤いバケツをもったクマさんもいるので、なんだか「みつけた!」という感じで楽しかったのを覚えています。
小さな双子の野ねずみは、いつも仲良しで、いつも相手を思いやって生活や遊びを楽しんでいて、絵本の中の世界は平和で、愛で溢れています。
森もお家も、家具も食べ物も、明るい彩色で、自然とともに生活していて、小さなことに驚き、喜び、楽しみ… 困ったことがあれば、頑張って解決しようと頑張ります。 大人になって絵本を開いてもやっぱり楽しく、子どもの頃の幸せな時間や思い出とともに蘇ったり、人生の大切なものが見えてくる宝物のような絵本です。
印象に残る絵本、感動する絵本、思い出とともにある絵本、考えさせられる本、様々ありますが、昔も今も人気で、どの世代にも愛されている、本当に名作中の名作だと思います。
「ぐりとぐら」が生まれたのは1963年。
はじめはお母さん、お父さん向けの雑誌「母の友」で、読み切りのお話として登場したそうで、その時のタイトルは「たまご」だったそうです。
そして、その年の12月に、月間絵本「こどものとも」(93号)で、絵本「ぐりとぐら」が登場したとのことです。
お話を作った中川李枝子さんと、絵を描かれた山脇百合子さんは姉妹で、お二人で、ぐりとぐらシリーズの他にも、私の大好きな「いやいやえん」をはじめ、たくさんの童話や絵本を世に送り出してくれました。
妹さんの、山脇百合子さんは3年前に、お姉さんの中川李枝子さんは昨年10月に、お亡くなりになっています。
とてもとても残念ですが、ふたりが送る出してくれた数々の絵本や童話は、これからも、子ども達の心を明るく楽しくしていってくれることでしょう。
そして、お二人が描いた世界のように、今の平和な日常が、永遠に続いてほしいと願っています。
※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。