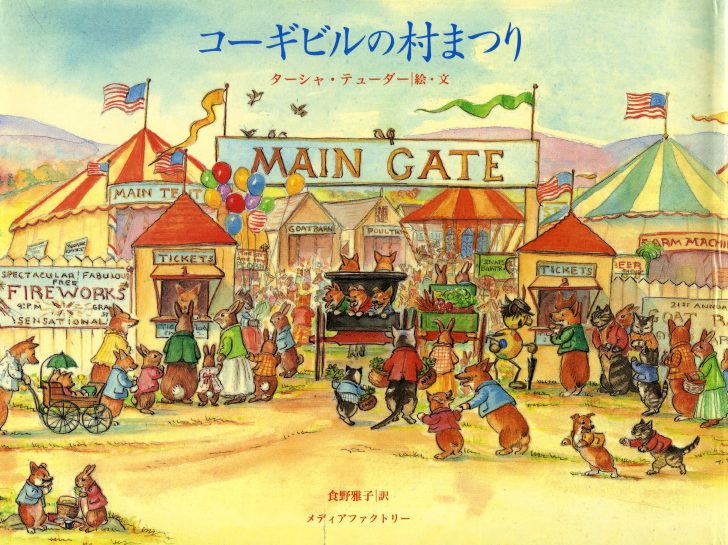ひろすけ童話「むく鳥のゆめ」
集英社版
浜田廣介 作
深沢邦朗 画

昔、夜眠る前に母によく読んでもらった絵本。とても古い絵本ですが、大切にしています。
浜田廣介という、とても有名な童話作家の作品なので、何作か同じお話の絵本が出版されていますが、実家にあったのはこの絵本でした。
以前にブログに記した「ないた あかおに」もこの方の作品です。
お話は…
広い野原の真ん中に立つ古いくりの木。その木のほらの中に、むく鳥の子どもと、とうさん鳥が住んでいました。
秋になり、すすきの ほ が白くなると、とうさん鳥は、その ほ をくわえて
すのなかに持ってきて温まり、やがて寒い冬を迎えても、そのすすきのほ のおかげで困らずに暮らせていました。
寒く天気の悪い日が続いたある日、むく鳥の子はふと、母さん鳥に気がつきます。遠いところへ出かけたと思っていたけれど、なかなか帰ってこないのを気にして、とうさん鳥に尋ねます。
とうさん鳥は、かあさん鳥がもう この世にいないとは言えず、
「いまごろは、うみの上をとんでいるの。」
「もう、いまごろは、やまをこえたの。」
と、聞くむく鳥の子に、「ああ、そうだよ。」と、答えるだけでした。
なかなか帰ってこないかあさん鳥が恋しいむく鳥の子は、木に残った たった一枚の葉っぱが、かさこそ、かさこそ…というだけでも「おかあさんかな」と、思ってしまっていました。
でも、寒くなり、風が今にも茶色くなった枯れ葉をもぎ取ってしまいそうです。
それを見た むく鳥の子は…
とても寂しく、切ないお話。でも私は、このお話を母親に何度か読んでほしいといったのでしょう、読んでもらった事をよく覚えています。
子どもにとってお母さんという存在が、どれほど大切なものか、どれほど恋しいものかが、切々と伝わってくるこの絵本を、読んでもらった声や腕枕してもらったぬくもりを思い出すのです。
前回、ブログに記した「ねないこだれだ」と同様に、むく鳥の子がお母さんを恋しがり、葉っぱのゆれる音にお母さんを感じて眠る姿に、心がきゅっとなったり、そばにいるお母さんを感じて安心したり という相反する感情が、子どもの感受性を豊かに成長させてくれるのかな、だから、印象的で、よく覚えているのかなと、思いました。
またこの絵本は、深沢邦朗という童画家が描いておられる 挿絵もとても素晴らしく、秋から冬に移り行く季節や、雪がしんしんと降ってくる様子、木の色やすすきの穂のあたたかそうな風合い、色合いの少ない季節に反してきれいな羽のむく鳥の子の姿など、印象的な素晴らしい挿絵です。
寒くなって来たこの季節に、読んであげたい名作童話です。